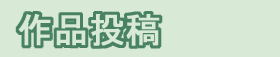
| (2024年10月) < *印 旧仮名遣い > | |
|
水野 康幸(HP運営委員) |
|
| ○ | はな | ||
| 炎天を忘れし如く枝延ばし山吹揺るる秋風吹けば 入院せし友のことを案じおれば赤まんま咲き白まんま咲く 山霧の山肌覆い道覆う白き世界に閉ざされて居り |
|||
| 評) 前:炎天の夏から山吹が秋風に揺れるまでの季節の移り行きが表現されている。中:病気の友のことを心配していると花が咲いているのが見える。単純化が優れた歌。後:山霧が覆って来てあたり山道が一面白に閉ざされてしまった。情景がよくわかる。 |
|||
| ○ | 原田 好美 | ||
| 日溜まりに女郎花の花群れ咲いて寄り添いながら風に揺れおり 車椅子を夫が緩やかに押しくるる散歩する二人の影重なりて |
|||
| 評) 前:女郎花が寄り添いながら風に揺れている。後:夫が車椅子をそっと押してくれているが、前の歌と同じように自分たちも寄り添いながら散歩している。「二人の影重なりて」が適切な表現になっている。 |
|||
| ○ | つくし | ||
| 雄大な瀬戸大橋と島々を鷲羽山より見下ろす夕暮 今は亡き犬と歩みし森林公園秋の紅葉の景色変わらず |
|||
| 評) 前:鷲羽山より見下ろした風景をありのままに詠っているが、「雄大な瀬戸大橋」に重点がある。後:かつて犬とやって来た公園で亡くなった犬を偲んでいるが、紅葉の風景はいまだ同じである。 |
|||
| ○ | 湯湯婆 | ||
| くまぜみの飛びこみ来たり出でゆきぬ間取りを知るや一筆書きに 丹精をこめた柿の木実りなく佇むわれに日照り雨ふる |
|||
| 評) 前:「間取りを知るや」がややユーモラスで、作者は蝉が一筆書きに家の中を舞い、出て行った、と感じている。後:懸命に育てた柿の木に実りが無いので佇んで見ている吾に、容赦なく日照り雨が降ってくる。悲しいと言わず単に「日照り雨ふる」と言っているのがよい。 |
|||
| ○ | 鈴木 英一 * | ||
| 蜻蛉たちその自在なる飛び方はオスプレイより優れてをりぬ 天岩戸神社の奥の洞窟に神々の姿見ゆる心地す |
|||
| 評) 前:やや説明的になったが、蜻蛉はオスプレイより優れていると詠んでいる。後:神社の奥の洞窟を拝めば、神が住んでいるかの如くである。 |
|||
| ○ | 夢子 | ||
| フランスのオリンピック見るを目標に生きて今度はロスアンゼルスか 目標があれば励みに生きてゆく私一人のオリンピックよ |
|||
| 評) 「目標があれば励みに生きて行く」という言葉に同感する。誰も目標を持って生きているが、作者はそれをオリンピックに置いている。軽い歌だが面白い。 |
|||
| ○ | はずき | ||
| 祝日に五千人もの従業員ストライキ始めしハワイのホテル 交渉後三日間なるストライキ太鼓叩いて歩道占領す |
|||
| 評) 祝日だというのに大勢でストライキするハワイのホテル。太鼓叩き歩道を占領してまでストライキするホテルにあきれて作者は見ているようだ。珍しい光景を見て歌にしている。 |
|||
| ○ | 但馬 吟太郎 * | ||
| 朽ちかけし曼殊沙華の花みるごとにこの往生は遠く思ほゆ 椎の木にころりころりと成れる実を食めるかけすが頬の黒きこと |
|||
| 評) 前:曼殊沙華の花は往生するには遠い、と擬人法を使って詠んでいる。後:カケスがころり、ころりと椎の実を食っているが、その様子を更に詠んで欲しかった。そのカケスの頬が黒い、と歌の観点が移動している。 |
|||
| ○ | 紅葉 | ||
| 観戦のひけた後らし両国駅は土産袋もち乗りこむ客ら 対応を要する指摘はなかったと勝手に思う審判は如何に |
|||
| 評) 前:相撲観戦の時間が終わり、両国駅に相撲関係の袋を持って電車に乗り込んで来る乗客が多い、というのである。後:相撲観戦で審判の「物言い」に関して作者は疑問を持っているようだ。 |
|||
| ● | 寸言 |
| 「実景をそのまま具体的に詠む」というアララギの歌の詠み方をしていると、時に「現実主義だけでは、どうも面白くない。少しひねった詠み方をする方が面白そうだ。」と考える人も出てきそうである。雑誌「新アララギ」の中にも、最近では一読して意味の取りにくい歌も登場してきているように思う。分かりにくい歌はなぜ良くないのだろうか。部分的に特にふつう使わない語を用いると全体の意味を把握しにくくなる。歌は一読してさっと情景が浮かぶのがよいが、そのためには全体の意味が初めから把握できていなくてはならない。茂吉が「無くて叶うまじきものはただひとつなり」という聖書の言葉を引いて「単純化」の説明していたが、歌では形式上複雑なように見えても、言いたいことはただ一つでなければならない。歌はバラバラなものを組み合わせるのではなく、ひとつのもの、茂吉の言葉では「実相」に入り込んでつかむことが大切である。それが個性なのである。個性をだそうとして初めから目指すのではなく、実相をめざせば、個性はおのづから出て来ると私は思う。したがって、一読して意味が不明瞭なもの、全体で何が言いたいのかが、はっきりしない歌がホームページに出てきた場合は、私の方から作者の意図をはっきりしてもらえるよう要請し、そこから私と共に歌を改稿してゆきたい。 水野 康幸(HP運営委員) |
|
| ← → |