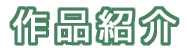
|
(平成27年7月号) < *印 現代仮名遣い>
|
|||
| ○ | 三 鷹 | 三宅 奈緒子 | |
| この一つ詩形にただに頼り来ぬ若きより今にながき日月を いまさらに何求むるかひと日ひと日心つくして詠ひゆくのみ |
|||
| ○ | 東 京 | 吉村 睦人 | |
| 仙翁の鮭色の花を目に浮かべ今夜はベッドに眼を閉ざす 廃れたる園にてあれど入り来て残り咲く花を見てまはりたり |
|||
| ○ | 奈 良 | 小谷 稔 | |
| 近江の湖雨に暮れたる闇深し友の情けに春の旅寝す 比叡より激ちて下る清き水幾年ぶりぞ鳴る水に沿ふ |
|||
| ○ | 東 京 | 雁部 貞夫 | |
| インディカ米選びてカレーを振舞ひし土屋文明親しと思ふ 細長きインディカ米を一か月飽かず食みにきオアシスの旅に |
|||
| ○ | さいたま | 倉林 美千子 | |
| 電話にて大会の指揮をとる夫の整然として九十と思へず 人の名の出でねば傍らにゐよといふ夫の知人など全部は知らず |
|||
| ○ | 東 京 | 實藤 恒子 | |
| 『明月記』の超新星爆発の三つの記録は世界最多といへり 平安の天文博士安倍清明の記録を知り得て『明月記』に記しき |
|||
| ○ | 四日市 | 大井 力 | |
| 八百年修覆せざるを誇りゐる御輿が社殿に納まるところ 父と兄の忌ををさめ来て裏山の風も夜更けとなれるやさしさ |
|||
| ○ | 小 山 | 星野 清 | |
| 発行所への往き来に仰ぎし高架工事その高きうへ今まさにゆく 頭上はるかに見上げし高架を今ゆくか再びの命わが賜りて |
|||
| ○ | 福 井 | 青木 道枝 * | |
| 実験機の下めぐりつつ語らうは物理の徒にしてわが夫わが子 一瞬に花びら凍らせ割りて見す母わがためのデモンストレーション |
|||
| ○ | 札 幌 | 内田 弘 * | |
| 恍(とぼ)けつつじっと見ている老いが居てそれを見ている俺もまた老い 霊柩車いま目の前を過ぎてゆく生きてる吾ら覇気なくたむろ |
|||
| ○ | 横 浜 | 大窪 和子 | |
| 人のかなしむ声かと紛ふ日々に乗る京浜東北線軋むその音 大空を翔けゆく翼四回転ジャンプして開く広き両手は |
|||
| ○ | 那須塩原 | 小田 利文 | |
| 老いづきし吾が身には辛き作業にて数へる言葉声に出でたり 労働の辛きをなぐさめ歌ひ合ふと聞きしことあり今ならわかる |
|||
| ○ | 東広島 | 米安 幸子 | |
| 風か鳥か庭に芽生えし山桜石に添ひ立つ一木となれり 散りかたの花に立ちたる今夕の後ろ姿はわれのみが知る |
|||
| ○ | 島 田 | 八木 康子 | |
| クックパッドにツワのレシピは七十九ともあれ灰汁を抜かむ湯を張る 筍の穂先と共にとろ火にてあつさり炊かむ先づは一品 |
|||
| ○ | 名 護 | 今野 英山(アシスタント) | |
| 幾重にも寄せ来る波はまだ荒し地震(なゐ)から四年われにも流る 旅をすることなど止めし琉球つばめ海の青さを背(せな)にまとひて |
|||
| ○ | 所 沢 | 斉藤 雄太 * | |
| 何気ない人の言葉にイライラす我の心は狭いのだろうか 桜散り道路をおおう花ビラに四月の雪が降りかかりたり |
|||
| ○ | 松 戸 | 戸田 邦行 * | |
| 我が手助け無用とはっきり言い放つその意気や良し踏ん張れ息子 子育ても終えて仕事も順調なり何が心に穴を開けしか |
|||
| ○ | 東 京 | 加藤 みづ紀 * | |
| 窓からの風そよぐ午後辞書めくる留学中の土曜日と似て ルーブルに人かいくぐりモナリザの最前列に立ちき十代のわれ |
|||
| ○ | 尼 崎 | 有塚 夢 * | |
| 重きこの足枷なれどいつの日か我のみの持つ翼になるわ 「暗さ」とて泥濘のごとき闇もあれば安らぐ宵の色合いもある |
|||
| ○ | 奈 良 | 上南 裕 * | |
| 土の付く殻を双葉の先に乗せ木通の種のこぞり芽を出す 「それ、どういうこと?」切れかける人の目を見据え低く抑えて話し始める |
|||
| ○ | 高 松 | 藤澤 有紀子 * | |
| かばん一つで去りゆく我を見送るは五年間見慣れし桜の木のみ 歯をくいしばり慣れぬ仕事に精を出す支援学校上りと言われたくなくて |
|||
|
『宮脇武夫全歌集』より (昭和十六年七月発行) 大雨の過ぎつるあとの日の暑さ傘乾かししかばつよき香ぞする 宮脇武夫は、中途失明者であり病弱で臥床する日々であった。その生活から聴覚・嗅覚・触覚など鋭い神経と生きた言葉でもって捉え、詩の真実を歌おうと努めた。昭和十三年 カタル性肺炎にて死去。三十六歳であった。
|
|||
| ← → |