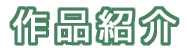
|
(平成27年9月号) < *印 現代仮名遣い>
|
|||
| ○ | 三 鷹 | 三宅 奈緒子 | |
| 亡き父のみもとに早も行きたき日まだまだ行けぬと思ふ日とあり 室内を杖にてやうやく歩む身のせめて吹かれたし六月の風に |
|||
| ○ | 東 京 | 吉村 睦人 | |
| 猟銃にて応戦したりし民間人戦死にはならず殺人とさる 防衛産業の社長が大きな鞄提げ総理官邸に入りてゆく夢 |
|||
| ○ | 奈 良 | 小谷 稔 | |
| 能筆の父の頼まれて書きし墓碑過疎の極まるふるさとに在り 動脈瘤また声帯の手術すれど父の齢の二倍のいのち |
|||
| ○ | 東 京 | 雁部 貞夫 | |
| 流山の富士塚高さ六メートル道は急なり火山岩敷く 富士塚の道はゑぐれて危ふかり人には言はず手の平の汗 |
|||
| ○ | さいたま | 倉林 美千子 | |
| この沼に河童が棲むと友言ひき水漬く葦むらの辺りが騒ぐ 思はざる華麗なる会に大きリボン付けて独りもの言ひ終はる |
|||
| ○ | 東 京 | 實藤 恒子 | |
| 半夏生の白く茂れるみぎはべを歩みて憂ひを遣らはむとする 満ちきたる潮の勢ひにビルの影ゆらぎ目守れるわれも揺らげり |
|||
| ○ | 四日市 | 大井 力 | |
| 太古の海にいまだ単細胞の植物より目の機能変異に受けし動物 海中のナメクジウオを祖として生き残るため目を進化させし人類 |
|||
| ○ | 小 山 | 星野 清 | |
| 今も続く造山運動をネパールの大地震に改めて思ひ知りたり 見覚えの屋根は傾き大方は瓦礫となりて映るカトマンズ |
|||
| ○ | 福 井 | 青木 道枝 * | |
| 二百年かなたの欧州よりとどく音色わが今のこころ掻き立つ わが手より生まれくる音またことば求め求めて漸くのひかり |
|||
| ○ | 札 幌 | 内田 弘 * | |
| 発車後の吾が居ぬホームをビニールの袋が旋毛風に飛び行く 電話メモが簡単すぎて解らない妻も説明出来ぬ夕ぐれ |
|||
| ○ | 横 浜 | 大窪 和子 | |
| ほそほそと鳴く鶯を幾たびか庭に聞きとめこころ潤ふ 笹を吹く風のおと寄する波のおと遥かなるものに向かひ佇む |
|||
| ○ | 那須塩原 | 小田 利文 | |
| 拒否権のあらば行使せむデメリットのイメージしかなきマイナンバーは 障害の重き子が一人暮らす時悪用されずやマイナンバーは |
|||
| ○ | 東広島 | 米安 幸子 | |
| 草叢に首のべ雉の高鳴けりかなり離れて二羽の啄む くさむらに見え隠れして啄みし二羽低く飛ぶ声せし方へ |
|||
| ○ | 島 田 | 八木 康子 | |
| 朝夕の六時に低く鳴る鐘の余韻静かに腑に沁みとほる 既存新幹線の三倍の電力消費とやリニア中央新幹線は |
|||
| ○ | 名 護 | 今野 英山(アシスタント) | |
| この湾に嵐避けしベトナム船万国津梁の久米島ここは 手造りの泡盛蔵を訪ひゆきて黒麹の醸成つぶさに見たり |
|||
| ○ | 松 戸 | 戸田 邦行 * | |
| 戦時下のパイロットらが描きし本脚色としても止まらぬ涙 三匹の猫と妻とが添い寝するこの幸せを永遠に守りたい |
|||
| ○ | 東 京 | 加藤 みづ紀 * | |
| 空の下飲みしビールにほてりし顔上げればライトに飛ぶホームラン オレンジの小さな灯りの下で塗るピンクのマニュキア夜風に乾かす |
|||
| ○ | 奈 良 | 上南 裕 * | |
|
猫の子を埋める者を責めるまい手軽に切身を購う現実 |
|||
| ○ | 尼 崎 | 有塚 夢 | |
| 哀しみの藍色深く空満たす夕焼けになどならずともよい 見るものが違えば景色が異なれば開放感となる横浜の空 |
|||
| ○ | 高 松 | 藤澤 由紀子 * | |
| ベテランより我より優れた同僚よりも児は頼りなき我を選びぬ 崩れかけた心の再びよみがえる我をたのめる親と児あれば |
|||
|
『松倉米吉歌集』より (大正3年) わが握る槌の柄減りて光りけり職工やめていくたび思ひし 松倉米吉は「アララギ」に大正2年に入会し、古泉千樫に師事して、作家に励んだ。短歌が唯一の「生きがい」となって職工生活を続けたが、肺病を発病し悲劇の内に夭折した歌人である。大正7年に母を失い、住み込みの職場の養子となり、娘と恋仲になるが、病癒えることなく25歳の若さで一生を終わる。その歌は、ありのままの哀しみを何の衒いもなく率直に詠った歌として私たち後進に今でも残っている。
|
|||
| ← → |