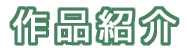
|
(平成28年9月号) < *印 新仮名遣い >
|
|||
| ○ | 東 京 | 吉村 睦人 | |
|
風船蔓の小さき花に来てをるは蜂の類か蠅の類か |
|||
| ○ | 奈 良 | 小谷 稔 | |
| 老残を詠みあふ中にひとり混じる若きは鉄削る職を失ふ 湯に浸り安らぎゐるに壁面の装置は止まず時を示せり |
|||
| ○ | 東 京 | 雁部 貞夫 | |
| 春となりし大山思ふ谷に入り山ふところに独活掘る友よ 独活かじり飛騨高山の古酒をくむ遠き友らに会ふ心地して |
|||
| ○ | さいたま | 倉林 美千子 | |
| モニターの動く病室に垣間見し看取りの人の昼一人なり 意識なき媼はその人の母ならむ呼ぶでもなくて立ち尽しゐる |
|||
| ○ | 東 京 | 實藤 恒子 | |
| 汚染水を封じ込むる凍土壁その一割は氷らざるとぞ 光環を纏ひそびゆるスカイツリー何の恩寵ぞ正目に見たり |
|||
| ○ | 四日市 | 大井 力 | |
| ふるさとの小学校舎増築を伝へ来ぬ津波予想に移住人口増えて さかしらに是非を言ふなと襲ひ来る津波か古代より幾たびとなく |
|||
| ○ | 小 山 | 星野 清 | |
| 風呂場にて倒れ警察が来てゐると寝むとするを呼び出されたり 看取らるるなく唐突に逝きたるか半年が程われより若く |
|||
| ○ | 福 井 | 青木 道枝 * | |
| 陽のそそぐ木道のうえ先々を飛びゆくトンボ濃きその影よ ふうわりと飛びゆくトンボその影と一つになりて切株の上 |
|||
| ○ | 札 幌 | 内田 弘 * | |
|
髪の湿りを拭いつつ行く地下歩道濡れているのは吾ばかりなり |
|||
| ○ | 横 浜 | 大窪 和子 | |
| 君逝きたりと聞きしこの夜パソコンに交ししメール繰りて読みゆく 柔きこころ滲ますその笑顔ヒロシマ訪へるオバマ氏の面に |
|||
| ○ | 那須塩原 | 小田 利文 | |
| 子と在りし週末を思ふ蒲公英の綿毛が風に揺れゐる朝 カーラジオに地震速報無きことを確かめて出づ朝の慣ひに |
|||
| ○ | 東広島 | 米安 幸子 | |
| 人を車を止めて待ち待つ広島にゆふかたまけてオバマ氏降り立つ 資料館にわづか十分何かひと言と期待せしかど願ひもむなし |
|||
| ○ | 島 田 | 八木 康子 | |
| モーニングコールそれとも目覚ましか止まず未明の風に乗り来ぬ 取り壊す蔵より出でしと「静岡県月刊アララギ」我に届きぬ |
|||
| ○ | 名 護 | 今野 英山(アシスタント) | |
| 沖縄戦のさきがけなりし座間味島ケラマツツジの赤々と咲く ダイバーの行きかふ浜に敵上陸の日付記せり読む人もなく |
|||
| ○ | 松 戸 | 戸田 邦行 * | |
| 病おし歌評会に参加する歌と向き合うすがたわが眼に 春の過ぎ夜空かすみて星なきは人の栄華か人の奢りか |
|||
| ○ | 東 京 | 加藤 みづ紀 * | |
| 午後五時の退社の時刻近づけば晴れ間の見えて空高くなる 蛍光灯静かにともる残業中ふいに聞こえるドライブの曲 |
|||
| ○ | 東 京 | 桜井 敦子 * | |
| ATMよ君はどこから見てるんだい「画面の上に物置くな」とは 休みの日何かしなきゃと思いつつ昼寝のネコの隣で過ごす |
|||
| ○ | 高 松 | 藤澤 有紀子 * | |
| かけられる「是非に」の言葉に引きずられ二か月の勤務が一年となる 見よここに社会が求める我が居る困った困ったと言ってはみても |
|||
|
土屋テル子の歌 道のべの細きぎぼしゆもをしみ採りておくるるわれを夫のうながす 土屋テル子は土屋文明先生の夫人です。昭和23年、群馬の川戸に疎開しているころで食糧の大変きびしい時代です。擬宝珠(ぎぼしゅ)とは野草です。なんのためにこの野草を採っているのかわかりますか。食べるためです。 一首目、夫というのは 土屋先生です。遅れる私を先生が促す。二首目、叢はくさむらと読みます。きぎすとは鳥の雉です。雉のヒナがいたのですね。 三首目、結句は抜き飽かぬかも 面白いようによく抜けて楽しい。 四首目、擬宝珠は掌くらいに大きい葉です。葉を棄てるのは葉の、じくの部分を食べるからです。 五首目、落葉が腐葉土になってやわらかい上に座って葉をちぎっている所です。山草の採集が具体的にこまやかに詠まれています。
|
|||
| ← → |