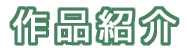
(令和4年2月号) |
|||
| ○ | 東 京 | 雁部 貞夫 | |
| 神妙なる心となりて歌の神守らせたまへと鈴の音を聴く 北野天神にて 皆既蝕をはれば事なき望の月「堀川」歩む吾らを照らす |
|||
| ○ | 東 京 | 實藤 恒子 | |
| 気に入りの形見の和服にかこまれて愉しむ自由飛翔の自在 寝転がりて鳥の姿とその声を電子辞書に聴く愉しくもあるか |
|||
| ○ | 四日市 | 大井 力 | |
| 光る星従はせゐる四日月山脈に入る前のかがやき 夕星を見に出て何の脈絡もなきにふるさと石の下の父母 |
|||
| ○ | 小 山 | 星野 清 | |
| 土俵上に倒れし市長を介護する看護師を降ろさむとせし行司もありき われに過ぎし遊びのひとつにエヴェレスト望まむとせし半月の旅 |
|||
| ○ | 柏 | 今野 英山 | |
| 緊急事態つづく小樽の運河沿ひ灯りともりて靴音冴える 百年前の商工会議所ホテルへと変りゆくのか石造のままに |
|||
| ○ | 横 浜 | 大窪 和子 | |
| 感染二年国々に異なるコロナ事情国民性といふを思ひぬ 鋼打つ鐘のやうなる音聞え向かひの丘に工事始まる |
|||
| ○ | 能 美 | 小田 利文 | |
| ネコジャラシをしとど濡らして過ぎし雨の残しゆきたる大きなる虹 白山の初冠雪を隠しゐし雲も動きぬ送迎に向かふ |
|||
| ○ | 生 駒 | 小松 昶 | |
| 詫びながら闇の奥処に母の骨落とすや返るかすかなる音 袋の中に小さく収まる吾が母を十七年待つ父に届けぬ |
|||
| ○ | 東 京 | 清野 八枝 | |
| スキー合宿の子らと来たりし奥志賀の黄葉あかるき白樺林 ポールつき夫に声かけ下りゆくブナ原生林の渓谷の道 |
|||
| ○ | 西東京 | 中村 眞人 | |
| 秋深み冷えゆく朝の出勤まへ茂吉歌集をひととき開く 「負けないぞ」と強き握手をたまひたる吉村先生をただに畏れき |
|||
| ○ | 島 田 | 八木 康子 | |
| 火葬場の隣の台より遺族の声金具が出ない骨が違ふと 紛ふなくチタン出づべし我もまた大腿骨頭置換したれば |
|||
| ○ | 小 山 | 金野 久子(アシスタント) | |
| 仏壇に仕舞ひ置きたる会葬礼状あまた読み返し日暮れとなりぬ 乾く眼に目薬注して潤ほすに秋の陽射しはかくも眩しく |
|||
|
〇茂吉の最上川観 (小谷 稔 著『アララギ歌人論』より抽出、( )は小松注) 最上川は茂吉の故郷近くを流れる大河であるが、歌に登場するのは蔵王山の24歳に比べると意外に遅く、46歳のときである。
最上川水嵩まされどしかすがにやまがはのごとおもほゆるかも 『ともしび』昭3 最上川は茂吉にとり生命をもった自然として茂吉の「いのち」に呼応し共鳴して、さかまく濁流であったり月明を湛えた神秘の静かさであったり緩急動静休むことがない。刻々瞬時も停滞することなく、変化してやまない無常相である。(四首めは)敗戦後の冬における茂吉の沈痛な悲傷を強調して説くむきもあるがこれも「無常相」の一である。流れと吹雪と相せめぐ自然が逆白波となって底知れぬ荒涼感を呈している。 なげかひを今夜はやめむ最上川の石といへども常ならなくに 動かぬ石と動きやまぬ流れとともに無常相と見て茂吉はかろうじて不安に耐えている。最上川は茂吉にとって戦後の悲傷と流離の身を慰藉するもの、病気の鬱屈、「追放」の不安を鎮めるもの、さらに活力をあたえるものであった。 |
|||
| ← → |