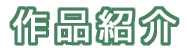
(令和5年2月号) |
|||
| ○ | 東 京 | 雁部 貞夫 | |
|
ヒマラヤの勇者も今や意気地なし階段見上げ溜息しばし 「断捨離」と得意になりて言ふ勿れ老いの命を棄てよと言ふか |
|||
| ○ | 東 京 | 實藤 恒子 | |
| 道の辺のフェンスの赤き烏瓜捥ぎ取りて終の講座に出でぬ 画眉鳥の声杜鵑終の講座全力を出し切りわが悔のなし |
|||
| ○ | 四日市 | 大井 力 | |
|
日を置かず国葬ふたつ営まれある筈のなき魂おもふ 気が付けばあの人が居ないと言ふ様な世の閉ぢ方が良しと思ひぬ |
|||
| ○ | 小 山 | 星野 清 | |
| エージシュートを誇りしは八十になる前か物食へず横たはりゐるといふ友 酒の席にひとり飲まずに送りくれし面倒見のよき旧き友なりき |
|||
| ○ | 柏 | 今野 英山 | |
| 勲一等あはれなるかな目の前の利益大事にてその身亡ぼす 一票のためならサタンと手を結ぶ神の顔したサタンと知りて |
|||
| ○ | 横 浜 | 大窪 和子 | |
| 動員されしロシアの兵士ら過ちて同士討ちさへするとはまことか 武器買ふか棺桶買ふかとは何のこと理解に悖る侵攻いつまで |
|||
| ○ | 札 幌 | 阿知良 光治 | |
| 三日前に会ひたる母は亡きがらとなりて戻りぬ古りたる家に 納棺師の女性に化粧ほどこされ生きゐるごとき母を哀しむ |
|||
| ○ | 能 美 | 小田 利文 | |
| 爽やかに去らむ願いの失せゆきて朝見し山も雲に隠れつ 見送りの中の一人の顔去らぬ今宵のビール苦しとも苦し |
|||
| ○ | 生 駒 | 小松 昶 | |
| 稔り田の向かうの窓より流れくるピアノ調律の短調の音 母の遺ししあまたの短き鉛筆にキャップ付くまま使ふことなし |
|||
| ○ | 東 京 | 清野 八枝 | |
| 映像研のカメラ構へてキャンパスに月蝕を追ふ孫の写メール 展覧会のマチスの絵葉書送りたり反抗期の子ら育てゐる次女に |
|||
| ○ | 島 田 | 八木 康子 | |
| ジョン万次郎の「漂客奇談」の写し出づ嘉永七年わが祖の筆 手から手へ書写を重ねて渡りしか未知なる世界へのあつき思ひに |
|||
| ○ | 小 山 | 金野 久子(アシスタント) | |
| 土井晩翠作詞の校歌簡明な言葉こそよけれ今なほ歌ふ 戦地さへ潜む地球の影映し蝕はすすみゆく物思ふ間も |
|||
「伊藤左千夫の九十九里詠」(小谷稔『アララギ歌人論』より。表記は一部変えてある(小松)) A(明治42年)
茫洋とした大自然に対峙してその大自然を併呑するほどの雄渾な格調をなしている。それ以前の B(明治32年)短歌三首 は、子規以前とは思えない万葉調が見られる。また、 C(明治35年)短歌三首 は子規に学び、それぞれ、大柄な万葉調、忠実な写生、軽妙な趣向が出ている。が、こう見ると、BやCは習作的な段階のもので、Aのような稀に見る豊潤、雄渾、荘重な雄編に到達し得たことは瞠目に値する。その契機となったものの重要な一つは、明治三十七年に始まった信州の山を主とする自然との接近であると思われる。Aの歌までに6回も信州を訪ねている。 D(明治37年) 雄渾な信州詠、骨太の写実で堂々たる調子であり、左千夫の山岳詠の開眼である。自然の要所を確かに把握して観念的な形式美を脱している(下線―小松)。 E(明治39年)「蓼科游草」より Dの八ヶ岳遠望とは異なってその山に入り宿るという接近と、左千夫を素朴な敬愛の心で歓待した信州の歌人たちへの親愛は左千夫の抒情を理想的に醸成して写実と抒情が渾然とした調子の中に一体となったこの作者独自の世界を見せている。これらの山の秀吟を生んだ余勢を駆ったかのように、Fが作られた。 F(明治40年)「磯の月草」 浜に注意が向けられ空が詠われていない35年のCと比べ、全く面目を一新している。空や雲を詠いこんで、雄大さを醸している。 G(明治41年) この年は3回も蓼科に行った。「蓼科雑詠」より D,E,Gにおける八ヶ岳を遠望した崇高感、蓼科の温泉に象徴される人間を抱擁する温かな自然、また蓼科の「花の原天つ国原」という浪漫的な自然など、左千夫の自然を見る目はこまやかに自由に広がりを見せている。そして、Aが作られたのである。 |
|||
| ← → |