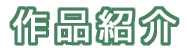
(令和5年7月号) |
|||
| ○ | 東 京 | 雁部 貞夫 | |
| 歌よみは「遠」より「杳」を好むらしぼんやり暗い形容なるに 茂吉・文明二時間語つてよしと言ふ芳美の「キエフ」も忘るるなかれ |
|||
| ○ | 東 京 | 實藤 恒子 | |
| 鬱蒼たる桜の古木の一年をつくづく眺め二十三年 その孫に恭子さんと呼ばせゐし妹の心解る気がする |
|||
| ○ | 四日市 | 大井 力 | |
| 入所して襁褓当てられたちまちに足の立たざる友になりゐつ 歌詠みの大方が持つ身の奥の翳りも記憶も捨てたる友か |
|||
| ○ | 柏 | 今野 英山 | |
| 囲炉裏にて煙管吸ひゐし祖父の顔言葉すくなく色黒かりき 香りよき刻みは「桔梗」祖父くれしキセルにて吸ふ深く一服 |
|||
| ○ | 横 浜 | 大窪 和子 | |
| 胸の中におのれ促し動くもの朝が来たのだ起きねばならぬ ランダムな水玉模様にさくら散る細き坂みち風あたたかし |
|||
| ○ | 札 幌 | 阿知良 光治 | |
| いち早く伸びたる独活を根元より切りて酢味噌にあへて食ひたり ふくよかな叔母の遺影を仰ぎつつちやん付けで呼ばれし記憶のめぐる |
|||
| ○ | 能 美 | 小田 利文 | |
| 人事票ヒラヒラ振りつつ呼び止めて思ひもかけぬ異動先を指す 心沈み立つ洗面所に「おはやう」と子は来ぬ頬に米粒付けて |
|||
| ○ | 生 駒 | 小松 昶 | |
| 賃六千円なりし下宿はヴォーリズの設計にて築百年を超ゆ 外壁の剥がるる白亜荘の吾が部屋は現代美術のギャラリーとなる |
|||
| ○ | 東 京 | 清野 八枝 | |
| 時雨過ぎまた降る今宵のコンサート友と来りし野外劇場に 美しきブルージュの岸辺白鳥は卵抱けり白き花の下に |
|||
| ○ | 広 島 | 水野 康幸 | |
| 隣席に赤子をあやす母のゐて病院に長くわが番を待つ いつの間にか喜寿になりたり部屋に積む本の終活なさねばならず |
|||
| ○ | 島 田 | 八木 康子 | |
| いつまでも結論遠き友の電話吉凶こもごも駆け巡るまま 刈り込みし芝の中よりタンポポのこの春増えて三ところに咲く |
|||
いてふの葉嵐にもまれにほふ夜の窓にして一人怒をこらふ 五味保義の第四歌集『一つ石』の前半(昭和25年〜29年)の作品より。 この十年間も、昭和二十年以来引きつづきアララギ刊行の事務に従ひ、アララギ発行所を自宅に置く関係上、一日もその事から離れられず(中略)旅行の歌なども、アララギの用件で地方に出向いた時のものが、その大部分を占める実情であります。 六首目は「悼斎藤茂吉先生」と題した七首中二首目、七首目は「大石田」と題した六首中四首目の作品。 ※旧字体は新字体に改めて掲載した。 |
|||
| ← → |