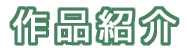
(令和5年9月号) |
|||
| ○ | 東 京 | 雁部 貞夫 | |
| 給食にこほろぎ食らふ今の世か「美しい日本」いづこ行きしや どの候補も子供のためと連呼する先ゆき短き老忘るなよ |
|||
| ○ | 東 京 | 實藤 恒子 | |
| 平成二年「保渡田」を読めば誘はれしわれより若き亡き友思ふ 入江眞知子様 誘はれ土屋先生の跡尋めぬ平成二年歌会を終へて 全国歌会 |
|||
| ○ | 四日市 | 大井 力 | |
| 十万年核のゴミ地底保存をうやむやに決めて列島入梅のとき 芍薬の前に屈みておのづから花のこころにひとりの遍路 |
|||
| ○ | 小山 | 星野 清 | |
| 運転を止むればたちまち老いわれに友らも街も遠くなりゆく 右顧左眄することのなく真実を貫きて定年までわれは勤めき |
|||
| ○ | 柏 | 今野 英山 | |
| みづからの楽句待ちたるフジコ・ヘミングかすかにリズムをとる指見える 綴れ着に白髪束ねるピアニスト人は人なりわが祖母に似る |
|||
| ○ | 横 浜 | 大窪 和子 | |
| 週一度のケアハウスを「お仕事」と捉へてよりきみはゆくを拒まず かくほどに互の内実が暴露され世に広まるに止めぬか侵略 |
|||
| ○ | 札 幌 | 阿知良 光治 | |
| 母の遺骨意外に重しと思ひつつ霊園へ向かふ納骨の今日 母のみ骨父のみ骨のその上にそつと納めて墓穴を閉づ |
|||
| ○ | 能 美 | 小田 利文 | |
| 送迎の途中見かけゐし洋菓子店初めて寄りぬ移動日前日に 明日よりは新たなる道に仰がむかこの送迎路に親しみし山 |
|||
| ○ | 生 駒 | 小松 昶 | |
| 俯ける自閉の少女は伴奏に合はせ顔上げシンバル連打す アゴラコンサート 去年はドラムを二拍のみ叩きし少年は曲の半ばを越えて打ちゆく |
|||
| ○ | 東 京 | 清野 八枝 | |
| 清らかに河鹿の声のとよもせり銀山の湯をわが浴みをれば 空も雲も黄金色に輝く水平線に沈む落日の終の一瞬 |
|||
| ○ | 広 島 | 水野 康幸 | |
| 韓国語の授業終はりぬ十分間のスピーチが今日はうまく出来たり 朝毎にベランダより見る遠き山カール・ブッセの詩を思ひ出づ |
|||
| ○ | 島 田 | 八木 康子 | |
| 歌心ある人続々入会しよぎる杞憂も朧となりぬ 心潤ふやさしき夢に目覚めたり降り継ぐ小雨にいざなはれしか |
|||
このたび、故小谷 稔先生の末弟、ドイツ文学者の小谷裕幸さんが『ある限界集落の記録、、、昭和二十年代の奥山に生きて』(冨山房インターナショナル)を出版された。かねてより、先生のお話また歌や文章で、生まれ育った故郷が消えてゆく悲しみを認識していたが、この本で、そのご一家を中心にした地域の実情がより詳しく分かり、歌への理解もより深くなった。同時に、そのごきょうだいの殆どが文学に深く関わられてい、個人的にも書物を出版、また合同でも『はらから六人集』(正、続)を出されている。そしてその大きな要因として、学校や社会からよりも、ご両親とごきょうだいからの薫陶を強く感じた。そこで今回は先生の最終歌集『大和くにはら』からふるさとのご家族に関わるものを挙げてみたい。 父母の知らぬ悲しみ稲やめし故里は初めて注連縄を買ふ |
|||
| ← → |