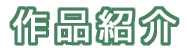
(令和6年1月号) |
|||
| ○ | 東 京 | 雁部 貞夫 | |
| 百円ライター買ふよりはるかに風情あり桃尻マークの安全燐寸は 開会にいまだ間のある喫煙所老友とわれ紫煙くゆらす |
|||
| ○ | 東 京 | 實藤 恒子 | |
| 砂嵐がわが足元に吹きつけて九十九里の浜に立ちつくす 紺青の海に真白き波立ちて寄り添ひゆくはやさし君かも |
|||
| ○ | 四日市 | 大井 力 | |
| 雨模様の今朝は山鳩の声聞かず誰も居らねば鳴き真似に呼ぶ 免許証返納をして廃車して人と言葉を交さずなりぬ |
|||
| ○ | 柏 | 今野 英山 | |
| 一千の討ち死に記す木柱もいつかは消えむ草深き中 矢切西蓮寺 五十にて家族を捨てて出家せしわが叔父常に乞食の旅 |
|||
| ○ | 横 浜 | 大窪 和子 | |
| 勝ち目なき戦も人はするものかハマスのイスラエル砲撃悲し はや店を閉ぢし菓子屋に花屋ありインボイス制度の導入されて |
|||
| ○ | 札 幌 | 阿知良 光治 | |
| 「先に逝くよ」と笑みゐるごとき妻の面涙堪へ得ず目を覆ひたり 妻の為にやつてやれることのなくなりて朝虚しく空を仰ぎぬ |
|||
| ○ | 能 美 | 小田 利文 | |
| モロヘイヤを食べしことなき妻のため茹でて刻みて豆腐に載せぬ フォグランプを点し通ひし塩原の山道浮かぶよ霧の夜道に |
|||
| ○ | 生 駒 | 小松 昶 | |
| 昼暗く銀杏の覆ふ普門院墓原広く迷ひつつ行く 高々と繁れる棕櫚の木の下に左千夫の墓のひそやかに建つ |
|||
| ○ | 東 京 | 清野 八枝 | |
| 秋草の原を飛び交ふアキアカネわが指に触る羽光らせて 「ああ生きてる」と木犀の香に声あげし退院の娘よ一年経ちぬ |
|||
| ○ | 島 田 | 八木 康子 | |
| 秋彼岸過ぎればすぐに正月と言ふを諾ふ齢となりぬ 古希過ぎて知りたる一つ心のみ若き日のまま変はることなし |
|||
| ○ | 広 島 | 水野 康幸 | |
| わが左脳に斯くも著き傷ありて医師示す写真を驚きて見る 妻が医院に持ち来てくれし韓国語版の村上春樹を一心に読む |
|||
松尾富雄 昭和14年アララギ入会。戦争をリアルに詠い土屋文明に認められて有名になった渡辺直己の友人。呉の高校英語教師。呉アララギ会は昭和10年に扇畑忠雄が呉に2年間居た間に盛んになり、土屋文明を2回呉に招いて歌会を開いたりしたが、扇畑が呉を去った後から戦後にかけて松尾富雄がこの会の中心となって活躍した。戦後、会員として「アララギ」の集Ⅰ欄に長く投稿。歌集は「水照波(みでりなみ)」と「鳰の住む沢」の2冊。 歌集「水照波」の後記から一部分を紹介する。 歌集「水照波」より 歌集「鳰の住む沢」より |
|||
| ← → |