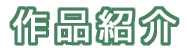
(令和6年5月号) |
|||
| ○ | 東 京 | 雁部 貞夫 | |
| 王の世継ぎ定まらば皇子ら消されゆく漢も明日香の御代もおぞまし バッキャヤロウ天に向ひて声放つ理不尽な奴に出会ひし夕べ |
|||
| ○ | 東 京 | 實藤 恒子 | |
| あしたより降り頻る雨ひねもすに寒さいやます立春の今日 八幡宮の宮司の一人娘にて小説を書かむ強き意志もつ |
|||
| ○ | 四日市 | 大井 力 | |
| 生涯にふたたび人の血を貰ひ癒えたる恩をしみじみ思ふ 鈴鹿嶺を越えゆく雲が空高く黄色のひかり含みて過ぎぬ |
|||
| ○ | 柏 | 今野 英山 | |
| 冬ざれの空に咲きみつる寒桜かなはぬ願ひつぶやいてみる 千枚田の景をまるごと取り入れて離宮の庭は今に保てる |
|||
| ○ | 横 浜 | 大窪 和子 | |
| 起き抜けに激しき揺れに襲はれぬ東京湾震源震度4のニュース キッチンに掛けゐし時計午前九時テーブルに落つ電池外れて |
|||
| ○ | 札 幌 | 阿知良 光治 | |
| 満面の笑みの写し絵を遺影にと妻言ひてゐしそれの一枚 雪解けの雫の音にまどろめば笑顔の妻の夢に出でくる |
|||
| ○ | 神 戸 | 谷 夏井 | |
| うな傾す白き小花を雪の小鈴と言ひ給ひし文明先生慕はし 宵の内に夫のくれたる葛根湯効き始むらし喉の腫れ引く |
|||
| ○ | 能 美 | 小田 利文 | |
| 大地震の二時間前に投函せし吾が年賀状も届きたりしか 吾が存在無きこの家を街を思ふ明け方の夢の続きの如く |
|||
| ○ | 生 駒 | 小松 昶 | |
| 人減りて閉ぢむとしたる歌会なり吾が呼びかけに人ら集へり 小学校の友の表札確かめて呼び鈴押すに反応のなし |
|||
| ○ | 東 京 | 清野 八枝 | |
| 骨折の松葉杖つきし我を助け食器洗ひ来し夫の十二年 桜咲く景を想ひて鳥居坂に「植治」の庭を夫と眺めぬ |
|||
| ○ | 島 田 | 八木 康子 | |
| 槙垣より抜き出で輝く棗の実小さき林檎かと見し幼き日 本ばかり読んでる人はだめよねと呟かれしがまた蘇る |
|||
| ○ | 広 島 | 水野 康幸 | |
| 灌木林のかげに黄金のひかり落とし月は夜更けのみづうみ照らす あたりの音なべて消し去り渓谷は耳を聾して流れつつあり |
|||
「宮脇武夫全歌集」から *宮脇武夫は明治36年(1903年)千葉県生まれ。19歳東京商科大学専門部に入学、22歳で上記大学を卒業、守屋商会に入社、横浜小学校夜学部嘱託で英語、簿記,商事要項を教授。24歳両目失明して退職。翌年にアララギの会員となり昭和13年(1938年)36歳で死去するまで歌を詠んだ。 ・盲ひたる君なりしかばわがこゑをなつかしといひて近く居りにき *佐藤佐太郎によれば、時々彼の家で歌会が開かれたが、その中で「彼の批評は論理的で細かく、言葉の味わいを重んぜられた。自説を堅く固持して譲らない所がありこれは頑固というより、熱心と自信を思わせた。また座中誰よりも雄弁であった。」と言う。 晩秋の光あまねき櫟山馬子より先に馬のぼり来る |
|||
| ← → |