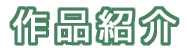
| (令和6年12月号) | |||
| ○ | 東 京 | 雁部 貞夫 | |
| 文鎮の代はりのハーケン錆びたれど俎嵓の完登記念 *谷川岳の西へ張り出した岩峰群 幾時間たちしや登攀の終着点岩の裂け目に竜胆そよぐ |
|||
| ○ | 四日市 | 大井 力 | |
| コロナ罹患に衰へし嗅覚おもむろに戻るを朝の卓に試しぬ 鯖雲が海へ海へとうごきゆく彼の世を思ひ見上げゐるとき |
|||
| ○ | 柏 | 今野 英山 | |
| リスボンにてまづ何するか中折れの手製の帽子をこの店に買ふ 植民地の苦き香りか深煎り珈琲アールヌーヴオーのカフェに味わふ |
|||
| ○ | 横 浜 | 大窪 和子 | |
| 酔芙蓉繁り翳れるキッチンの窓を開け閉めして過ぐる夏 ありがたう幸せだよといひながらベッドに入る夫に微笑む |
|||
| ○ | 札 幌 | 阿知良 光治 | |
| 朝採りの枝豆茹でて妻に供へ今日五十五年の記念日を伝へる 来年はエメラルド婚式よと言ひし妻の明るき声が甦りくる |
|||
| ○ | 神 戸 | 谷 夏井 | |
| おねだりと陰口きかれてまだ辞めぬ知事よあなたのプライドいづこ 若さゆゑと期待せし日の己恥づ人の痛みを知らぬ知事とは |
|||
| ○ | 能 美 | 小田 利文 | |
| 些細なる今日の不運も霧散せり高校球児の熱き試合に 新米にあらずとも良し店頭の能登棚田米に急ぎ足となる |
|||
| ○ | 生 駒 | 小松 昶 | |
| 八百キロ隔たる四人きやうだいの旅に集へり六十年ぶり 勘定奉行罷免されたる祖を偲び天守閣に見放く紀州の海を |
|||
| ○ | 東 京 | 清野 八枝 | |
| 卒業研修の父島に発つわが少女ら台風一過の青空の下 生命科学部 足ひれをつけし若きらのシュノーケリング珊瑚も魚も動画に揺れゐる |
|||
| ○ | 広 島 | 水野 康幸 | |
| 妻の微熱未だ下らず今宵また「吐き気する」と言ひ食事の準備す 「真理とは教へらるる無く自らにて発見すべきもの」と父の言ひにし |
|||
| ○ | 島 田 | 八木 康子 | |
| ただ事のみ冗舌に詠む歌誌を閉づ切れば血の出る歌に会ひたし 戦時下は遺書も検閲受けしとぞ黄ばめる和紙の中の髪と爪 |
|||
今回は伊藤左千夫(1864元治元年~1913大正2年)の歌の紹介です。 左千夫は千葉県九十九里浜の近くに生まれ眼病のため法律学校を中退し、現在の東京都江東区錦糸町の辺りで牛乳搾取業を始めます。東大入学前後の貧しい土屋文明を支えました。正岡子規との論争後、明治33年四歳下の子規の門下に入ります。明治35年(1902年)35歳の子規の没後、その後継の歌人をまとめ、歌誌「馬酔木」ついで明治41年(1908年)創刊の歌誌「アララギ」の中心歌人となり、森鷗外の観潮楼歌会に招かれるなどして、島木赤彦、斎藤茂吉らの後進を育てます。その作風は子規ゆずりの写生歌に、雄大で切実な感情がこめられています。
牛飼
が歌よむ時に世のなかの
新
しき歌大いにおこる
没後刊行された「左千夫歌集」の巻頭歌 |
|||
| ← → |