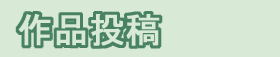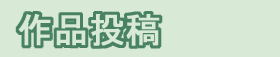 |
|
|
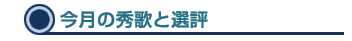 |
|
|
|
(2012年7月) < *印 新仮名遣い> |
|
小谷 稔(選者・編集委員) |
|
|
|
| 秀作 |
|
|
○
|
|
金子 武次郎
|
|
残生か余生か余命か知らねども生きねばならぬわがこの生を |
|
|
評)
残生、余生、余命というよく似た言葉を重ねたのは残りの日が限られている老いの「どうでもいいではないか」という不快感の心理だと解しておもしろいと思った。「生きねばならぬ」という強い意志の表現が尊い。 |
|
|
|
|
○
|
|
ゆの字 *
|
|
瓦待つブルーシートの隙間から青草伸びる二年目の夏
|
|
|
評)
東北大震災の被災地であろう。「瓦待つ」は被災地ではいろいろの制約があって葺けないのであろう。「ブルーシートの隙間から青草伸びる」という写実が深刻さよく捉えている。 |
|
|
|
|
○
|
|
星 雲
|
|
歳若き妻がゆつくりわれの歩に合はせて朝の路地を散歩す
|
|
|
評)
夫婦では若い頃から夫が妻をかばうのが一般であるが夫が老いてゆくと妻から労られるようになる。作者もこの歌のように妻を見るまでには抵抗があったであろう。それを経た穏やかさである。 |
|
|
|
|
○
|
|
文 香 *
|
|
若き日の自分に出会いそうになる小路を避けて街に紛るる
|
|
|
評)
若い頃は誰でもが懐かしいものとは限らない。挫折、失意、屈辱その他さまざまな負の思い出がある。それを甦らせそうな小路に来て急いで街の雑踏に身を紛らす。小路がよく効いている。 |
|
|
|
|
○
|
|
紅 葉
|
|
さ夜なかの樋を流れる雨の音そばにはきみの寝息も聞こゆ
|
|
|
評)
さ夜なかの樋を流れる雨の音、作者の神経を集中した心情は安らぎなのか何かの不安なのか、そばのきみの寝息を聞きながら思いに耽る余韻がある。 |
|
|
|
|
| 佳作 |
|
|
○
|
|
波 浪
|
|
妻とわれの会話険しくなりたるに気付きて素早く犬は逃げたり
|
|
|
評)
ここでは犬も家族の一員で夫婦の会話にこもる気配まで感じとっている。犬によって夫婦間の心情を巧みに捉えている。 |
|
|
|
○
|
|
Heather Heath H
|
|
納屋に錆ぶる父を押したる車椅子母保ちしを今日手放さん
|
|
|
評)
老いた両親の思いのこもった車椅子である。乳母車と対照的に老いてから使う車椅子にこもる思いは切ない。 |
|
|
|
○
|
|
もみぢ
|
|
城址より舞ひあがりたる花吹雪水面を染めて池を覆ひぬ
|
|
|
評)
下句が上句としっくり結びついて美しい落花の作になっている。花に集中した捉え方がよい。 |
|
|
|
○
|
|
山木戸 多果志 *
|
|
ようやくに暑き季節が近づきて遺跡の森の緑眩しき
|
|
|
評)
森の若葉はいいものであるがこの作は歴史的な「遺跡の森」というので風景に厚みが生まれている。 |
|
|
|
○
|
|
古賀 一弘
|
|
補聴器は無用とばかり高らかに囀り零す高尾山かな
|
|
|
評)
「補聴器は無用とばかり」は小鳥の囀りのひびきのよさをよく表現している。高尾山かなという「かな止め」は結びがしまらない。「高尾山こめ囀り零す」などはどうか。 |
|
|
|
○
|
|
石川 順一
|
|
我が部屋のハープの香り消臭と芳香を得て安眠をする
|
|
|
評)
ハープを安眠という生活に取り入れている点に独自な生活感がある。 |
|
|
|
○
|
|
なの
|
|
献体し葬儀その他一切無しあの人らしと笑顔になれり
|
|
|
評)
こういう死後の始末もあるのですね。人の死についての作なので結句の「笑顔になれり」はまだ再考の余地があるでしょう。たとえば「ひとりうなずく」のように。 |
|
|
|
|
| ● |
寸言 |
|
|
今度ここでお会いするのは来年ということになりますがまた作品を見るのを楽しみにしています。いろいろの標語かありますが、標語というのは作者の個人的、個性的な内容でなく、だれでもどこにでも通じるように作られています。短歌はその標語とは丸反対でその作者の捉えた個性的なものが必要です。注意一秒、怪我一生は標語ですが、短歌は、対象との一回きりの出会いの感動を言葉にするものです。
小谷 稔 (新アララギ選者・編集委員)
|
|
|
|
|
|
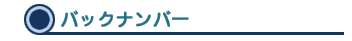 |
|
|