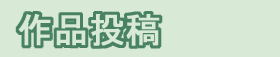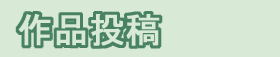 |
|
|
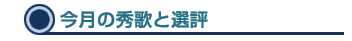 |
|
|
|
(2017年2月) < *印 新仮名遣い > |
|
大井 力(新アララギ選者)
|
|
|
|
| 秀作 |
|
|
○
|
|
ハワイ アロハ *
|
|
施設より連れ帰りたる父母とまた囲みたり新年の膳を
我の手にすがりて風呂に浸かりいる母が大きなため息一つ |
|
|
評)
人は父母より生を享け、育てられ介護して世を過ごす。宿世の循環をかく繰り返す。美しくもはかない。これも現実の断面である。 |
|
|
|
|
○
|
|
時雨紫 *
|
|
新年の「初心忘れるな」のスピーチに夫の誘いを例に話しぬ
ほろ酔いに二人歩いて帰る道ハイビスカスの雌しべ際立つ |
|
|
評)
このスピーチは家族単位の談話を想定する。御主人のアタックは徹底していたのであろう。それを家族の前に披露する。あたたかいものを感じる。2首目もそういう歌だ。 |
|
|
|
|
○
|
|
太等 美穂子 *
|
|
膝までの雪になずみて帰りくる子を辻にまち足踏みしている
あかぎれの痛みわすれて打ちあげし小豆を筵にひろげて干しぬ |
|
|
評)
昔懐かしい雰囲気の歌。子を待つ母の姿はいまも変わらない。情感のある歌である。 |
|
|
|
|
○
|
|
かすみ *
|
|
「行ってきます」いつものようにほほえんで妹嫁ぐ歳晩の朝
み社の椿描かんと筆をとる元旦客の姿忘れて |
|
|
評)
淡々としていて情の感じられる歌である。しかも温かい。 |
|
|
|
|
○
|
|
鈴木 政明 *
|
|
透き通る川面を渡りくる風に明日を語りて二人歩みぬ
戦闘機が青きみ空に飛行雲一筋ひきて西に去りたり |
|
|
評)
何か明るい。読むものも救われる感じがする。温かいのも更にいい。 |
|
|
|
|
| 佳作 |
|
|
○
|
|
金子 武次郎 *
|
|
せめて子等に迷惑かけじとつつしみていつしか至る齢八十
平均の余命とは何天よりの授かりものと思い至りぬ |
|
|
評)
生命の循環というか、宿世の営みというか、こうやって人は老いる。まさに授かりであろう。寂しいが現実の目の前には何かが近づく。いい歌である。 |
|
|
|
○
|
|
紅 葉 *
|
|
腰痛と筋肉痛と見通しのたたぬ仕事で始まる今日か
しばらくはからだ休めむジョギングもジムもプールも思うことなく |
|
|
評)
暗鬱の世代の思いであろうか。何も思うことなく過ごして拓けて来るものに期待したい。自らのなかにきっかけはある。 |
|
|
|
○
|
|
原 英洋 *
|
|
萎れたる花殻摘みて鉢植えのシクラメン疎らになりてしまいぬ |
|
|
評)
手を加えても滅ぶものはほろぶのか。天候のせいであろうか。自然とはきびしいものだ。 |
|
|
|
○
|
|
夢 子 *
|
|
我が腹の上に眠りしラッキーを起こさぬように暫しまどろむ |
|
|
評)
ペットは家族の一員であるが、犬との思いの交流を描くことは難しい。きっとかわいいという思いが強くでるからであろう。難しい。 |
|
|
|
|
| ● |
寸言 |
|
|
今月も生活に密着して詠まれた歌が多く、いいことだと素直に思った。問題はその生活の中の「心の襞」というか陰影がどうでているかだと思う。あかるく温かい歌もいいがなんともいえない懐かしい陰影のあるものがいいと思うのだが、えてしてそういうものを狙うと観念的になったりする。難しいものだ。しかし繰り返し同じ作業をやっているうちに「ふっ」と天から授かる場合がある。ひたすら待つだけでもいいのかもしれない。
大井 力 ( 新アララギ選者)
|
|
|
|
|
|
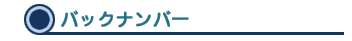 |
|
|