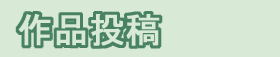
| (2019年5月) < *印 新仮名遣い > | |
|
八木 康子(新アララギ会員) |
|
|
○
|
山水 文絵 * |
||
小さき手がそっと放しし四段目の積み木崩れず共に拍手す |
|||
| 評) お孫さんのお守りをする温かな眼差しがまっすぐに伝わってくる一連。 一首目は最後まで推敲して、よりリアルに瞬間を切り取ることができた。 |
|||
|
○
|
文 雄 * |
||
声がやや大きくなって来たるゆえ妻の電話の漸く止むか |
|||
| 評) 高齢者の歎きなど表に出さず、どんな時も大きな懐で構えている作者の姿勢に好感が持てる。まわりの状況や人の気持ちを敏感にキャッチし、きめ細やかに受け止める生き方がこのような作品を生む源泉なのだろう。 |
|||
|
○
|
ハワイアロハ * |
||
| 会うたびに「どこから来たの」と問う婦人ハワイと聞きて今日も驚く 会いに来る家族がありて妬ましと呟きて顔をしかめる人も |
|||
| 評) 日本の施設に入所された父上と2週間を共に過ごした折の一連。施設ならではの、上記2首のような胸を打つ歌の他に「遠くより手を振りくれる車椅子の人に近寄りハイタッチする」など、持ち前のハイビスカスのような明るさがまぶしい作品もあって心地よい。 |
|||
|
○
|
中野 美和彦 |
||
| 「令和」にもやがて馴染まむさりながらほくそ笑む者らの企み許さじ | |||
| 評) 真正面から昨今の国政のありように挑んだ意欲作。時事詠は、気持ちを抑えて、表現は具体的に揺るぎなく、マスメディアの焼き直しでなく、と目指すところが高くて難しいとつくづく思うが、果敢に挑んでいかなければならない対象だと思う。 |
|||
|
○
|
時雨紫 * |
||
| 水田に白鷺の舞う時期が来ぬドジョウ探さん幼と共に 家中に餡とヨモギと笹の香の溢るる日々が令和にも来ぬ |
|||
| 評) 令和になろうとて昔と変わらぬ田園風景と、そこに流れる緩やかな時と共にある暮らしにホッとさせられる。 |
|||
|
○
|
菫 |
||
| 井戸水を運びて風呂に満たしゐし小さき母なりきくちなし匂ふ | |||
| 評) 母君を慕っての思い出をたどる一連。最終稿には出なかったが<「父さんは」と目を閉ぢしまま母は聞く既に逝きたる父の所在を>も胸に迫る写生歌。 |
|||
|
○
|
はずき * |
||
| イースター当てたロゴ付きアロハトート頭に被りおどける三才 | |||
| 評) 復活祭の一連。日本の地方に住む私には、なかなか映像として描ききれないもどかしさがあったが、推敲に努めてここまで鮮やかな写生に到達できた。 |
|||
|
○
|
夢 子 * |
||
| 目覚めれば朝日の中を漂うように痛みなき身に立ち返りたり | |||
| 評) 背骨の手術の翌朝だろうか「朝日の中を漂うように」は、目覚めた瞬間の無の境地の中ですっと出てきた言葉だろう。実体験者だけが言える得難い表現だと思う。 |
|||
|
○
|
鈴木 英一 * |
||
| ただ一人湯宿の離れの露天風呂間近に聴けり澄む鳥の声 | |||
| 評) 大涌谷の噴煙を見てきた後の安らぎの時がうまく捉えられている。他に「散歩道にいつも出会いし犬たちもが仲間見つけて我を無視する」は、見過ごしがちなところをのがさずキャッチした。このセンサーは大切にしてほしい。 |
|||
|
○
|
紅 葉 * |
||
| 出しそびれていたりし鯉を泳がせる娘が孫と訪ね来るらし | |||
| 評) 5月のある日の一仕事をさらっと詠んで情愛がにじみ、いい雰囲気を醸し出している。 |
|||
| ● | 寸言 |
土屋文明の『新編短歌入門』から、推敲中の一過程としての添削例を転載します。 原作 ・真夏日を思はするが如き暑き日に配達に出でぬ汗垂りにつつ 原作 ・はるばると訪ねしものをこの悩み老親見ては言はれざりけり 原作 ・語れば友の病は進むてふ見舞ひし吾のはかなかりけり 参考になさってください。 |
|
| ← → |