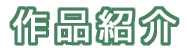
| (令和8年2月号) | |||
| ○ | 東 京 | 雁部 貞夫 | |
| 莨吸ふ自由もあるとぞサーヴィスの朝食クラム・チャウダー旨し 麦酒飲むことも忘れて歌談義文学館への恩義忘れず |
|||
| ○ | さいたま | 倉林 美千子 | |
| 古き写真の整理捗らず父の腕に笑みこぼるるは吾の棺に 時折はわが指に鳴りしトレモロの今はいづこの誰が弾ずるや |
|||
| ○ | 四日市 | 大井 力 | |
| あと二箇月すれば九十の日が待つよ工夫の果ての歌曲りゆく 逃水を追ふごと過ぎし一生か残りたるあと少しの時間 |
|||
| ○ | 柏 | 今野 英山 | |
| 終りちかき地球をさまよひ歩くごと熱にゆがみて白きこの道 自国ファーストは今だけファースト孫子らのパンや水には目を瞑りたり |
|||
| ○ | 横 浜 | 大窪 和子 | |
| 清澄庭園の池巡りゆき二十余年共なりし山仲間けふ別れの会 サッチャー女史メルケル女史の善政ありそに続きゆけ高市総理 |
|||
| ○ | 札 幌 | 阿知良 光治 | |
| 次々と来る同胞に応へつつ妻の三回忌法要を迎ふ 横浜の義弟が妻の幼き日語りて和やかな雰囲気戻る |
|||
| ○ | 神 戸 | 谷 夏井 | |
| 文明先生の山藍とのみ知りゐしに友は幾つも藍の種を言ふ 宿坊を数多備へしと聞く山に残る石垣古りて崩るる |
|||
| ○ | 能 美 | 小田 利文 | |
| ニューヨークに点りし一つ灯火よトランプに病む世界を照らせ マブダ二氏 備畜米に倣ひて備畜団栗を届けむこゑを聞く日は来ずや |
|||
| ○ | 生 駒 | 小松 昶 | |
|
種籾を貸し付け利息と収穫を民より徴すと正税帳は 正倉院展 蘭奢待の香りを嗅ぐと近寄るにガラスケースに額を打ちつく |
|||
| ○ | 東 京 | 清野 八枝 | |
| ふるさとに新設されし「国府多賀城駅」古代の鎮守府と政庁ありき われら幼く学びし坂上田村麻呂アテルイの悲劇を知らず過ぎ来し |
|||
| ○ | 広 島 | 水野 康幸 | |
| 紀元前二千年のエジプトの王の精巧なる小さき肖像 如何なる部屋に飾りをりしや子に乳を含ます紀元前の母子像あり |
|||
| ○ | 島 田 | 八木 康子 | |
| 敗戦前後の四たびの東南海地震なべて伏せられたりにし歴史 (昭和一九年より) 倒れ来し箪笥より助かりし嬰児か畳みて横に積みゐし布団に (生後数日の義弟) |
|||
落合京太郎歌集より
出来損が窯変天目になることを疑はず我は歌作り来ぬ |
|||
|
|