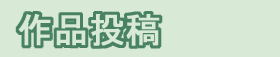
| 短歌をお寄せ下さい。作品には運営委員による指導があります。以下の手順でお願いします。
(1)「初稿」の提出。1人1か月に5首まで。自作未発表作品であること。 |
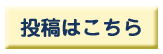 |
| (2026年1月) < *印 旧仮名遣い > | |
|
八木 康子(新アララギ HP運営委員) |
|
| ○ | 紅葉 | ||
| かからない謎は解けたり人影の見えぬ事務所と閉じた倉庫と なつかしのコーヒーの濃さもドタキャンの苦さに如かず一気に飲み干す |
|||
| 評) このサイトでは貴重な、現役で働く方の、今回は仕事にまつわる悲哀を詠う、身に迫る作品。 前:初句の「かからない」は、この前に「電話の」が付くと容易に理解できるのだが、この作者独特のなぞかけめいた詠法で、最後まで読んで初めてわかる形になっている。課せられた責務の果たせなかった現実は現実として、読者を楽しませようという茶目っ気もあるのかと思う。 後:日々の勤務の苦労を客観視して詠むこの強靭な精神力は、誰にも備わっているものだとはとても思えず、だんだん身内に向けるような心境にもなってくる。 |
|||
| ○ | つくし * | ||
| コンビニまで歩けぬ父がフランスの旅広告を今日も見てをり 雪の日にアイスを三つ食べし父逝くと知るなら怒らざりしを |
|||
| 評) 最近の出来事を詠んだ作品かと思っていたが、掲示板への書き込みからコロナ前の追想と分かり、改めて亡き父上への思いの深さに打たれた。 前:大切な人の鮮明な記憶は、いつまでもつい先ごろの事にように蘇るものだと、改めて思わされる一首。 後:思いがけない永遠の別れの後は、あれこれと後悔の念がよみがえるものだが、こうして作品にすることも、哀悼と共に自身への浄化に近づくものではないかと思う。 |
|||
| ○ | 夢子 | ||
| 去勢されおとなしくなりしラッキーを鼻で突いてココは悲しい 一日中追いかけ回したココのそば何事もなくラッキー座る |
|||
| 評) 他に「おとなしいラッキー抱いて謝りぬ人間の都合で父性奪いし」、最後には「耳先に去勢済みの切れ目入れラッキーのんびり骨を噛むなり」もあって、身につまされたり胸をなでおろしたりの一連だった。 前:家族同様に飼っていた2匹への思いが胸に迫り、「ココは悲しい」が作者の気持ちのようでもあり、短歌も映像のように鮮明に浮かぶものだと改めて思った。 後:ペットも家族そのものかと思い知らされ、健康で長生きできる原動力なのかもしれないと、教えられた気がする。 |
|||
| ○ | ふで * | ||
| 消えし名に地霊棲むかも宿山欠塚蛇崩蛇が窪など 観光客だけが蕎麦屋に群れなしてあとは寂しきシャッター通り |
|||
| 評) 2句までにすべてが集約されて、東京の江戸時代以前からの地名一連におどろおどろさが際立ち、一気に遥か昔が身近に迫ってくる。家康が幕府を構えようにも、めぼしい平野などすでにどこにも無く、幾筋もの河川が大雨・洪水の度に好き勝手に流れていた大湿地帯でしかなかった当時の関東一円に思いをはせると、この歌がリアルに立ち上がってくる。 後:上の句は、地方商店街それぞれによって違いはあるにしても、この下の句の潔いまでの切り口に、むしろ長い年月、共に人生を 重ねてきた同胞への情のようなものさえ感じさせられる。 |
|||
| ○ | 湯湯婆 | ||
| 二十キロの体重をかけ引く犬のリードを両手に腰ひくく歩く 人混みも他の犬も避けひっそりと一足ごとに呼吸かさなる |
|||
| 評) 前:初稿の「脚を病む友に代わりて愛犬の散歩をしたり年末年始に」を下敷きに鑑賞すると、友への熱い友情が胸に迫る。 後:ペットに家族同様の愛情を注ぐ作者ならではの心配りで、散歩の代行を引き受ける姿勢とはこういうものかと、頭が下がる。 初稿末尾の「独り居の心の友かエアコン付き二畳の小屋に飼われる犬は」に至っては、足を病むご友人の一日も早い快癒を祈るばかりだ。 |
|||
| ○ | 鈴木英一 * | ||
| 池のふち鴨らにも水は冷たきか芝生で顔を背に埋めをり あぢさゐの花は無残に垂れ下がれど脇芽はすでに枝に付きたり |
|||
| 評) 前:一気に襲ってきた厳冬の池、鴨たちもさぞ冷たかろうと詠う作者のまなざしが温かい。 後:夏まで咲く種類もあるアジサイも時期を過ぎたころの、作者のふとした発見。「重要なことは下の句に」とは、先月の「寸言」にあった言葉だが、まさにこういうことだと思った。 「近頃は足の衰へ思ひ知り妻と一緒に速歩に励む」も、なかなかこうはいかない向きもあると知るだけに、得難い一首として残したい。 |
|||
| ○ | 原田好美 | ||
| 振り向けば箱根の山に日が昇り霧のかかりて墨絵の如し デイケアの今年の書き初め「明」と書く背筋伸ばして思いを込めて |
|||
| 評) 前:この作者の短歌をどこまでさかのぼって読んでみても、明るく前向きな作風に、あらためてお人柄を見る思いがする。 後:そんな原田さんの気持ちのこもった書き初め、拝見させていただきたい思いにかられ、地域の文化祭などで見かける書道展にしても、背景にあるそれぞれの人生に一層の敬意を払わなければと、背筋の伸びる思いを新たにした。 |
|||
| ● | 寸言 |
| 年末年始のあわただしい時期にもかかわらず、投稿いただいたことに感謝しています。全員がほぼ並列と言っていいほどに優劣のない出来栄えでした。今月の<先人の歌>にも掲載した「出来損が窯変天目になることを疑はず我は歌作り来ぬ」に支えられて、私は歩んできました。紙と鉛筆さえあれば足り、月々のお仲間の作品に視野が広がり、新たな交友にも新天地にもつながる場として、ご友人や身近な方々にも、このホームページへのお声掛けをいただけると嬉しく思います。 八木 康子 (新アララギ HP運営委員) |
|
|
|